海外ドラマ(CSIシリーズ、LOST、HEROES/ヒーローズ、アグリー・ベティ等)のネタバレ感想をメインとしています。
26 .
November
以下の文章ではコールドケース3に関するネタバレを含みます。
ご注意ください。
コールドケース3 #21 入れ墨
ウィルはこの前のトラブルで降格され、デスクワークに励んでいます。
今週は誕生日なのにねえ、とみんなの噂の的。
ご注意ください。
コールドケース3 #21 入れ墨
ウィルはこの前のトラブルで降格され、デスクワークに励んでいます。
今週は誕生日なのにねえ、とみんなの噂の的。
センティネルの亡霊、それはひったくりに遭い、ホームへ転落死した新聞記者の女性の幽霊。
1945年7月に亡くなったロレーナ・キニーの事件は、殺人だったのではないかと、殺人課に依頼が入りました。
ある新聞が廃紙となり、編集部の掃除をしていたら「ローンデール駅 午後十時 このままではすまされない」とタイプ打ちの手紙が、ローのファイルから出てきたのだそうです。
ルーズベルト夫人は、女性記者を優遇し、その後ろ盾があったおかげで、ローも仕事に熱中できたのでした。ローは人生相談の担当者で、その関係で恨みをかったのではないか。彼女の死後、人生相談の担当を引き継いだのはライバルでもあったヘレンという女性。存命なので、話を聞きに行きます。
ローの登場で仕事を奪われる形になったヘレンは、あまり良い感情を抱いていませんでした。
にしても、三十過ぎて賞味期限切れってのは、酷いじゃないですか?!今の時代なら、なんてことはないけれど、あの時代には独身で、仕事に打ち込んでいる女性は、変人扱いですよ…。
賞味期限切れ扱いしたアーサーという男性に会いに行くと、前日に亡くなっていました。そこで、息子のデヴィッドが登場。ヘレンが家にやって来た事があると話をします。そこでノアという男性に会ったのが、ローの運命を大きく変えることになろうとは。ヘレンはノアに一目ぼれ。
デビッドにとっても、ノアは父親代わりだったそうです。
ノアは、オランダの生まれで、又従兄の子って、なんだかややこしいですよ。アウシュビッツから逃げてきたそうです。うーん、なんだか怪しいですよ。青年男子が、簡単に逃げ出せる場所じゃないでしょうに。
オランダでアウシュビッツといえば、『アンネの日記』を思い出しますね。
ノア・プールは絵を描くのが好きな老人です。
不法入国だったため、当時は黙っていたのだとか。家族も友人も皆死んでしまい、故国に帰ることはできない。そんな中出会ったローは、光そのものだったと語ります。
生き延びられたのは、絵が描けたから。家族たちを殺した、憎むべき看守たちを日々見つめて、肖像画を描いていたのだと。
ローは、ノアの記事を書くと誓います。同僚のバーディは、ローに代筆をしてもらい、度々助けられていました。そこで、編集長にもノアの記事の話をしていたのに、ローが急に記事に興味をなくしたため、喧嘩になったのです。バーディは、ノアと同郷だったヨハンナ・ホフマンを探し出しました。
ヨハンナはニューヨークに今も住んでいます。ローが亡くなったあの日からニューヨークに。
ウィルは、この歳になっての電話番に辟易しています。もう六十一歳なんですね。
この仕事は五十歳で引退するのが普通だそうで。
スティルマンもウィルと同じく、クズを追い回すのが好きで、この歳までこの仕事をやって来た。スティルマンは、自分のオフィスにウィルを呼び出します。ウィスキーをマグカップに入れて、男二人の乾杯です。格好いいなあ。
ニューヨークへ飛んだリリーは、ヨハンナの家を訪れます。
そこで始めて知ったローの死。ローに会わなければ良かった。
ヨハンナの表情には苦悶の色が浮かんでいます。
リリーがノアのことを尋ねます。
「ノアは死んだの。殺されたの。アウシュビッツで」
えええ、じゃあ、あのノアは誰ですか。
リリーが今のノアの写真を見せる。
「監視の人、アントンよ。番号を彫った人」
ヨハンナは左の袖をめくり、腕の内側に彫られた番号をリリーに見せます。
名前でなく、番号で管理されてた悲しい痕。
なぜアントンはノアのふりを?
民族浄化すべき相手になりたかったのか。
ローはナチに恋したと知っていたのか。
ノアこと、アントン・ビッカーはアトリエを引き払っていました。
自分の身が危うくなることには、人一倍敏感というべきか。
アントンを父親と慕っていたデビッドにも、真実が知らされました。でも、あんなに自分をかわいがってくれた人を、簡単に憎むなどできないことで。
ローがあの日に書いていた手紙を、デビッドはふとしたはずみに読んでいました。
「このままではすまさない。」
これは、アントンの過去を白日の下に曝す決意だったのです。
「私はこれからも生きていかなければならない」
えええ…アントン、そんな理由で逃げようとしたのですか。ローを殺したのですか。
「彼は僕より立派な男だ」
本物のノアが、肖像画を描いているときに語った話を、アントンは利用していたのです。
なら、なぜノアを逃がしてあげなかったのかと。
自分がノアになりきってしまうとは。あの戦争のいざこざで、アメリカにいたノアの親戚も写真など無くて、確認の仕様がなかったのかな…。必死で逃げてきたという人を、突き放すわけにはいかない。
人の両親を踏みにじって生きてきたわけだ。アントンは。
ナチであった自分をユダヤのノアに書き換えて。
逮捕されたときに、ヨハンナの姿も見えました。これで、少しでも彼女の苦痛が癒されればよいのですが。
1945年7月に亡くなったロレーナ・キニーの事件は、殺人だったのではないかと、殺人課に依頼が入りました。
ある新聞が廃紙となり、編集部の掃除をしていたら「ローンデール駅 午後十時 このままではすまされない」とタイプ打ちの手紙が、ローのファイルから出てきたのだそうです。
ルーズベルト夫人は、女性記者を優遇し、その後ろ盾があったおかげで、ローも仕事に熱中できたのでした。ローは人生相談の担当者で、その関係で恨みをかったのではないか。彼女の死後、人生相談の担当を引き継いだのはライバルでもあったヘレンという女性。存命なので、話を聞きに行きます。
ローの登場で仕事を奪われる形になったヘレンは、あまり良い感情を抱いていませんでした。
にしても、三十過ぎて賞味期限切れってのは、酷いじゃないですか?!今の時代なら、なんてことはないけれど、あの時代には独身で、仕事に打ち込んでいる女性は、変人扱いですよ…。
賞味期限切れ扱いしたアーサーという男性に会いに行くと、前日に亡くなっていました。そこで、息子のデヴィッドが登場。ヘレンが家にやって来た事があると話をします。そこでノアという男性に会ったのが、ローの運命を大きく変えることになろうとは。ヘレンはノアに一目ぼれ。
デビッドにとっても、ノアは父親代わりだったそうです。
ノアは、オランダの生まれで、又従兄の子って、なんだかややこしいですよ。アウシュビッツから逃げてきたそうです。うーん、なんだか怪しいですよ。青年男子が、簡単に逃げ出せる場所じゃないでしょうに。
オランダでアウシュビッツといえば、『アンネの日記』を思い出しますね。
ノア・プールは絵を描くのが好きな老人です。
不法入国だったため、当時は黙っていたのだとか。家族も友人も皆死んでしまい、故国に帰ることはできない。そんな中出会ったローは、光そのものだったと語ります。
生き延びられたのは、絵が描けたから。家族たちを殺した、憎むべき看守たちを日々見つめて、肖像画を描いていたのだと。
ローは、ノアの記事を書くと誓います。同僚のバーディは、ローに代筆をしてもらい、度々助けられていました。そこで、編集長にもノアの記事の話をしていたのに、ローが急に記事に興味をなくしたため、喧嘩になったのです。バーディは、ノアと同郷だったヨハンナ・ホフマンを探し出しました。
ヨハンナはニューヨークに今も住んでいます。ローが亡くなったあの日からニューヨークに。
ウィルは、この歳になっての電話番に辟易しています。もう六十一歳なんですね。
この仕事は五十歳で引退するのが普通だそうで。
スティルマンもウィルと同じく、クズを追い回すのが好きで、この歳までこの仕事をやって来た。スティルマンは、自分のオフィスにウィルを呼び出します。ウィスキーをマグカップに入れて、男二人の乾杯です。格好いいなあ。
ニューヨークへ飛んだリリーは、ヨハンナの家を訪れます。
そこで始めて知ったローの死。ローに会わなければ良かった。
ヨハンナの表情には苦悶の色が浮かんでいます。
リリーがノアのことを尋ねます。
「ノアは死んだの。殺されたの。アウシュビッツで」
えええ、じゃあ、あのノアは誰ですか。
リリーが今のノアの写真を見せる。
「監視の人、アントンよ。番号を彫った人」
ヨハンナは左の袖をめくり、腕の内側に彫られた番号をリリーに見せます。
名前でなく、番号で管理されてた悲しい痕。
なぜアントンはノアのふりを?
民族浄化すべき相手になりたかったのか。
ローはナチに恋したと知っていたのか。
ノアこと、アントン・ビッカーはアトリエを引き払っていました。
自分の身が危うくなることには、人一倍敏感というべきか。
アントンを父親と慕っていたデビッドにも、真実が知らされました。でも、あんなに自分をかわいがってくれた人を、簡単に憎むなどできないことで。
ローがあの日に書いていた手紙を、デビッドはふとしたはずみに読んでいました。
「このままではすまさない。」
これは、アントンの過去を白日の下に曝す決意だったのです。
「私はこれからも生きていかなければならない」
えええ…アントン、そんな理由で逃げようとしたのですか。ローを殺したのですか。
「彼は僕より立派な男だ」
本物のノアが、肖像画を描いているときに語った話を、アントンは利用していたのです。
なら、なぜノアを逃がしてあげなかったのかと。
自分がノアになりきってしまうとは。あの戦争のいざこざで、アメリカにいたノアの親戚も写真など無くて、確認の仕様がなかったのかな…。必死で逃げてきたという人を、突き放すわけにはいかない。
人の両親を踏みにじって生きてきたわけだ。アントンは。
ナチであった自分をユダヤのノアに書き換えて。
逮捕されたときに、ヨハンナの姿も見えました。これで、少しでも彼女の苦痛が癒されればよいのですが。
PR
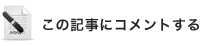
ブログ内検索
該当記事が見つからない場合、ブログ内検索をご利用ください。
カテゴリー
リンク
最新記事
(02/13)
(11/04)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
プロフィール
HN:
カンティーナ01
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
当ブログfadaises分館は個人が作成しているものです。関係各社様とは一切関係ありませんので、ご注意ください。製作・著作者の権利を侵害する意図は全くありませんが、なんらかの指摘及び警告を受けた場合には、速やかに文章を削除いたします。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
最新CM
カウンター
アクセス解析
フリーエリア
Powered by SHINOBI.JP
