海外ドラマ(CSIシリーズ、LOST、HEROES/ヒーローズ、アグリー・ベティ等)のネタバレ感想をメインとしています。
17 .
March
舞台「コペンハーゲン」を観てきました。
1941年第二次世界大戦の真っ只中で、ドイツ人物理学者のハイゼルベルグ(今井朋彦さん)は、恩師ボーア(村井国男さん)の元を訪ねる。ボーアはユダヤ系デンマーク人で、ナチス占領下のコペンハーゲンに妻のマルグレーテー(荒井純さん)とともに暮らしている。
死後の世界から三人は、この特別な日を振り返る。
物理、量子力学、相補性原理、不確定性原理、など高校のときに赤点だった話題が山のように出てきます。
この辺りの歴史や人物関係をもっと詳しく下調べうしておけば良かった…。
その点を除いたとしても、原子核爆弾の開発によって、人類の歴史を変えてしまうかもしれない葛藤に駆られるハイゼルベルグや、そんな彼を父親のように優しく見守るボーア、そんなボアーに苛立ちを覚えるマルグレーテ、三人の舌戦の凄まじさに思わず物語の中に引き込まれていきます。
舞台のセットを見た瞬間、原子モデルを思い出しました。三個の椅子が原子核で、歩き回る三人は電子。
改めて理系の勉強をもっと真面目にやっておけば良かったなと。物理や数学がどんなことに応用され、生活に、いや戦争にまで利用される危険も含んでいるとは理解していませんでした。
ある一人の人物のアイデアから、戦争時には何百万人もの人が殺害できる兵器が出来上がり、平和時にはエネルギーを造りだすものへと有効活用される。気付いていても知らないふりをするのか、先頭に立ち反対を訴えるのか、己から進んで陰の支配者となるのか。マルグレーテは、ハイゼルベルグの偽善者ぶりを見抜き、弾劾する。それはハイゼルベルグ本人も気付いていなかった真実。
ここだけでなく、そこにも、あそこにも同時に存在する可能性。
観察者がいることで、観察対象は何らかの影響を必ず受ける。
観客という観察者がいることで、あの三人にも何がしかの影響が与えられたのかもしれません。
1941年第二次世界大戦の真っ只中で、ドイツ人物理学者のハイゼルベルグ(今井朋彦さん)は、恩師ボーア(村井国男さん)の元を訪ねる。ボーアはユダヤ系デンマーク人で、ナチス占領下のコペンハーゲンに妻のマルグレーテー(荒井純さん)とともに暮らしている。
死後の世界から三人は、この特別な日を振り返る。
物理、量子力学、相補性原理、不確定性原理、など高校のときに赤点だった話題が山のように出てきます。
この辺りの歴史や人物関係をもっと詳しく下調べうしておけば良かった…。
その点を除いたとしても、原子核爆弾の開発によって、人類の歴史を変えてしまうかもしれない葛藤に駆られるハイゼルベルグや、そんな彼を父親のように優しく見守るボーア、そんなボアーに苛立ちを覚えるマルグレーテ、三人の舌戦の凄まじさに思わず物語の中に引き込まれていきます。
舞台のセットを見た瞬間、原子モデルを思い出しました。三個の椅子が原子核で、歩き回る三人は電子。
改めて理系の勉強をもっと真面目にやっておけば良かったなと。物理や数学がどんなことに応用され、生活に、いや戦争にまで利用される危険も含んでいるとは理解していませんでした。
ある一人の人物のアイデアから、戦争時には何百万人もの人が殺害できる兵器が出来上がり、平和時にはエネルギーを造りだすものへと有効活用される。気付いていても知らないふりをするのか、先頭に立ち反対を訴えるのか、己から進んで陰の支配者となるのか。マルグレーテは、ハイゼルベルグの偽善者ぶりを見抜き、弾劾する。それはハイゼルベルグ本人も気付いていなかった真実。
ここだけでなく、そこにも、あそこにも同時に存在する可能性。
観察者がいることで、観察対象は何らかの影響を必ず受ける。
観客という観察者がいることで、あの三人にも何がしかの影響が与えられたのかもしれません。
PR
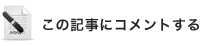
ブログ内検索
該当記事が見つからない場合、ブログ内検索をご利用ください。
カテゴリー
リンク
最新記事
(02/13)
(11/04)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
プロフィール
HN:
カンティーナ01
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
当ブログfadaises分館は個人が作成しているものです。関係各社様とは一切関係ありませんので、ご注意ください。製作・著作者の権利を侵害する意図は全くありませんが、なんらかの指摘及び警告を受けた場合には、速やかに文章を削除いたします。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
最新CM
カウンター
アクセス解析
フリーエリア
Powered by SHINOBI.JP
