海外ドラマ(CSIシリーズ、LOST、HEROES/ヒーローズ、アグリー・ベティ等)のネタバレ感想をメインとしています。
13 .
May
東京芸術大学美術館で5月28日まで開催中の"エルンスト・バルラハ"展に行ってきました。
同展のチケットで芸大コレクション展"大正・昭和前期の美術"も見られます。
チラシの作りが変わっていて、A4版たて書きを二枚繋ぎ合わせたものになってます。
美術館の三階がバルラハ展、地下二階が芸大コレクション展となっています。
入り口で三階から観賞するようお薦めされるので、エレベーターに乗って移動です。
バルラハ展では作品リストが見当たりませんでした。作成していないのかしら。
英語とドイツ語で書かれた、各章立てごとの解説書はありました。
こちらの邦訳は展覧会場で読むことができるのですが・・。
第1、2章では絵画を観ることができます。
繊細な筆遣いと、セピア色の落ち着いた色彩。
次第に絵画よりも彫刻への道を選ぶようになってゆく過程。
転機は第4章"ロシア旅行とベルリンでの芸術家としての成功"
ロシアといっても現在のウクライナに当たるところを、兄のニコラウスと約二ヶ月に渡って旅をしたのです。
その時の様々な経験が後の彼の作品に多大な影響を及ぼす事に。
物乞いをする女性の木彫り像があるのですが、彼女は頭からすっぽりと布をかぶり顔は全く見えないため、その表情を窺い知ることはできません。しかし、伸ばした手からその意思を感じとることができます。
今の日本ではほとんど物乞いをする人を見る機会はありませんが、海外に旅行するとその機会があります。
じっとうずくまったままで、掌を上に向けて何かを求める人。
異国の地で見かけた、あの人たちが目の前にいたのです。
バルラハにとっても、同じように衝撃的だったようです。
第5章"フィレンツェでの修行時代"
ここでバルラハは座禅や、武士道に影響を受けます。着物を身にまとった剣士の彫刻が数点見られます。
勢い良く斬り付けるその瞬間が、かたどられています。カトゥーン・ネットワークで放送しているアニメ「サムライ・ジャック」を思い出しましたよ。
第6、7章は戦争の時代。
宗教的なものや、反戦的な作品が多くなってきます。
版画も良かったのだけれど、残念ながらポストカードにはなっていませんでした。
戦死した兵士の慰霊象、実物が見たいなと思います。
同展のチケットで芸大コレクション展"大正・昭和前期の美術"も見られます。
チラシの作りが変わっていて、A4版たて書きを二枚繋ぎ合わせたものになってます。
美術館の三階がバルラハ展、地下二階が芸大コレクション展となっています。
入り口で三階から観賞するようお薦めされるので、エレベーターに乗って移動です。
バルラハ展では作品リストが見当たりませんでした。作成していないのかしら。
英語とドイツ語で書かれた、各章立てごとの解説書はありました。
こちらの邦訳は展覧会場で読むことができるのですが・・。
第1、2章では絵画を観ることができます。
繊細な筆遣いと、セピア色の落ち着いた色彩。
次第に絵画よりも彫刻への道を選ぶようになってゆく過程。
転機は第4章"ロシア旅行とベルリンでの芸術家としての成功"
ロシアといっても現在のウクライナに当たるところを、兄のニコラウスと約二ヶ月に渡って旅をしたのです。
その時の様々な経験が後の彼の作品に多大な影響を及ぼす事に。
物乞いをする女性の木彫り像があるのですが、彼女は頭からすっぽりと布をかぶり顔は全く見えないため、その表情を窺い知ることはできません。しかし、伸ばした手からその意思を感じとることができます。
今の日本ではほとんど物乞いをする人を見る機会はありませんが、海外に旅行するとその機会があります。
じっとうずくまったままで、掌を上に向けて何かを求める人。
異国の地で見かけた、あの人たちが目の前にいたのです。
バルラハにとっても、同じように衝撃的だったようです。
第5章"フィレンツェでの修行時代"
ここでバルラハは座禅や、武士道に影響を受けます。着物を身にまとった剣士の彫刻が数点見られます。
勢い良く斬り付けるその瞬間が、かたどられています。カトゥーン・ネットワークで放送しているアニメ「サムライ・ジャック」を思い出しましたよ。
第6、7章は戦争の時代。
宗教的なものや、反戦的な作品が多くなってきます。
版画も良かったのだけれど、残念ながらポストカードにはなっていませんでした。
戦死した兵士の慰霊象、実物が見たいなと思います。
PR
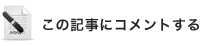
ブログ内検索
該当記事が見つからない場合、ブログ内検索をご利用ください。
カテゴリー
リンク
最新記事
(02/13)
(11/04)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
プロフィール
HN:
カンティーナ01
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
当ブログfadaises分館は個人が作成しているものです。関係各社様とは一切関係ありませんので、ご注意ください。製作・著作者の権利を侵害する意図は全くありませんが、なんらかの指摘及び警告を受けた場合には、速やかに文章を削除いたします。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
最新CM
カウンター
アクセス解析
フリーエリア
Powered by SHINOBI.JP
