海外ドラマ(CSIシリーズ、LOST、HEROES/ヒーローズ、アグリー・ベティ等)のネタバレ感想をメインとしています。
19 .
November
高校時代の友人がデザフェスにでブース出展しました。
学生のときは美術専攻してなかったのにねえ。と遠い目をしてしまいます。
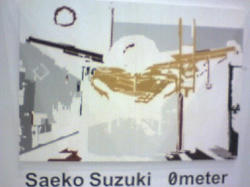
でもビラ配ったり、ポストカードが売れたりするの見ていると自分のことのように嬉しかったりします。
前回あまり話ができなかったので、今回は十数年ぶりにいろいろ話をしました
とはいっても、職場の愚痴になってしまうのが悲しいです…。
女二人で話している間に、友人の彼氏さんがブースのお留守番をしてくれていました。その間にけっこうお客さんが来ていたようで、まったく足引っ張ってばかりで申し訳ないです。
次は3月20日から23日まで、千住宿歴史プチテラスという所でグループ展を開催するそうです。「住む・暮らす空間」をテーマとした絵画や写真が展示されます。京成千住大橋駅から徒歩3分、北千住駅西口からは徒歩約十五分だとか。
学生のときは美術専攻してなかったのにねえ。と遠い目をしてしまいます。
でもビラ配ったり、ポストカードが売れたりするの見ていると自分のことのように嬉しかったりします。
前回あまり話ができなかったので、今回は十数年ぶりにいろいろ話をしました
とはいっても、職場の愚痴になってしまうのが悲しいです…。
女二人で話している間に、友人の彼氏さんがブースのお留守番をしてくれていました。その間にけっこうお客さんが来ていたようで、まったく足引っ張ってばかりで申し訳ないです。
次は3月20日から23日まで、千住宿歴史プチテラスという所でグループ展を開催するそうです。「住む・暮らす空間」をテーマとした絵画や写真が展示されます。京成千住大橋駅から徒歩3分、北千住駅西口からは徒歩約十五分だとか。
PR
20 .
October
国立西洋美術館にて来年1月6日まで開催中の『ムンク展』に行って来ました。
一階にあるコインロッカーはほぼ全て埋まっていました。一番下に空いている所があったのですが、今度は百円玉が無いことに気づきました。荷物を入れ、急いで両替をお願いしに行きました。階段の下にもロッカーがああるのですが、ついつい忘れて焦ってしまいます。
「叫び」がないのは残念ですが、「不安」と「絶望」があるだけでも、ここではない何処かへ心が連れて行かれます。そこから先へ一歩踏み出しては行けない。こちら側に踏みとどまらなければ、あの赤い空に飲みこまれてしまう。
「死と乙女」、骸骨の死と美しい女性が抱擁し、接吻をするかのように顔を付き合わせています。うっとりとした女性の表情。素敵だなあと思ったのですが、ポストカードはありませんでした。残念。
死に惹かれるかと思えば、強く生を意識させられる絵もあって、ムンクの揺れ動く心の中を、絵を通して観ていくのだと思いました。
常設展は、新館が工事中になっていて展示作品数が減っています。ダフィット・テニールスの「聖アントニウスの誘惑」が展示から外れたのは寂しい限り。
一階にあるコインロッカーはほぼ全て埋まっていました。一番下に空いている所があったのですが、今度は百円玉が無いことに気づきました。荷物を入れ、急いで両替をお願いしに行きました。階段の下にもロッカーがああるのですが、ついつい忘れて焦ってしまいます。
「叫び」がないのは残念ですが、「不安」と「絶望」があるだけでも、ここではない何処かへ心が連れて行かれます。そこから先へ一歩踏み出しては行けない。こちら側に踏みとどまらなければ、あの赤い空に飲みこまれてしまう。
「死と乙女」、骸骨の死と美しい女性が抱擁し、接吻をするかのように顔を付き合わせています。うっとりとした女性の表情。素敵だなあと思ったのですが、ポストカードはありませんでした。残念。
死に惹かれるかと思えば、強く生を意識させられる絵もあって、ムンクの揺れ動く心の中を、絵を通して観ていくのだと思いました。
常設展は、新館が工事中になっていて展示作品数が減っています。ダフィット・テニールスの「聖アントニウスの誘惑」が展示から外れたのは寂しい限り。
28 .
September
Bunkamura ザ・ミュージアムで10月25日まで開催中の「ヴェネツィア絵画のきらめき」展に行ってきました。
暑い、なぜいつも文化村に行く日は暑いのか…。
美術館の中は快適でした。
ティツィアーノ・ヴェチェリオ作『洗礼者ヨハネの首をもつサロメ』がチラシやポスターに載っていまして。
これはもう行くしかないでしょと。
お芝居の『ヴェニスの商人』を観てきたし、来月には『オセロー』が控えています。なんだかヴェニス三昧ですわ。これは来年行けってことでしょうか(←違います)
個人蔵の作品が、展示品の三分の一ほどを占めています。
パウロ・ヴェロネーゼ『エッケ・ホモ』とアントニオ・ザンキ『善きサマリア人』が良かったです。
ヨーゼフ・ハインツ『アイソンを若返らせるメディア』怪しい術を行うメディアの周囲にいる悪魔たちが、解説文にもありましたがヒエロニムス・ボスの描くそれに似ていて、じーっと見つめてしまいました。ちっこいのが暗闇にわさわさしているのです。
第三章は肖像画やサン・マルコ広場を描いたものなどがメインになっています。
一度でいいからカーニヴァルをこの目で見てみたいなと。
ガブリエル・ベッラ『トーガの着衣式』はお揃いの鬘とトーガを付けた人たちが大勢いて、何だか笑ってしまいます。『サンタルヴィーゼ広場でのサッカー』では昔も今もサッカーに熱狂するのは同じだなと。
『レデントーレの夜』では橋のたもとにお菓子の屋台が出ていて、そぞろ歩いている人たちが描かれています。
これで花火が上がったら最高なのに、と思ってみたり。
暑い、なぜいつも文化村に行く日は暑いのか…。
美術館の中は快適でした。
ティツィアーノ・ヴェチェリオ作『洗礼者ヨハネの首をもつサロメ』がチラシやポスターに載っていまして。
これはもう行くしかないでしょと。
お芝居の『ヴェニスの商人』を観てきたし、来月には『オセロー』が控えています。なんだかヴェニス三昧ですわ。これは来年行けってことでしょうか(←違います)
個人蔵の作品が、展示品の三分の一ほどを占めています。
パウロ・ヴェロネーゼ『エッケ・ホモ』とアントニオ・ザンキ『善きサマリア人』が良かったです。
ヨーゼフ・ハインツ『アイソンを若返らせるメディア』怪しい術を行うメディアの周囲にいる悪魔たちが、解説文にもありましたがヒエロニムス・ボスの描くそれに似ていて、じーっと見つめてしまいました。ちっこいのが暗闇にわさわさしているのです。
第三章は肖像画やサン・マルコ広場を描いたものなどがメインになっています。
一度でいいからカーニヴァルをこの目で見てみたいなと。
ガブリエル・ベッラ『トーガの着衣式』はお揃いの鬘とトーガを付けた人たちが大勢いて、何だか笑ってしまいます。『サンタルヴィーゼ広場でのサッカー』では昔も今もサッカーに熱狂するのは同じだなと。
『レデントーレの夜』では橋のたもとにお菓子の屋台が出ていて、そぞろ歩いている人たちが描かれています。
これで花火が上がったら最高なのに、と思ってみたり。
15 .
September
芸大美術館 陳列館にて9/17まで開催中の「自画像の証言」に行って来ました。
学生が卒業制作として自画像を描いたものを収集し、120周年記念事業の一つとして、今回陳列館で展示されることになったそうです。明治31年から始まり一時期途絶えたものの、現在も進行中だとか。
明治期は学ランを来て、真面目に描いているものが多かったです。
その年代によって、絵にも流行があるのかなと思ったり。
藤田嗣治さんはすぐに分かりました。
階段を上がると、昭和から平成の自画像が展示されています。
キャンパスを真っ黒に塗ったものや、静物画の中に自分の頭部石膏像を置いている人もいたり。
自画像という枠にとらわれることなく、自分を自由に表現した作品が増えてきます。
山口晃さんのがなくてがっかり。村上隆さんは、右斜めを向いた自画像で普段着の自分を描かれていました。松井冬子さんは、怖いという印象。
時代を問うことなく、嫌々描いている人、ノリノリで描いている人、は見ていてすぐに分かります。


その後はてくてく歩いて東京国立博物館へと向かいます。
特別展は終了していたのですが、常設展の特集陳列「キリシタン-信仰とその証-」を観たかったのです。ロザリオを禁止されたため、麻の縄に結び目をいくつも作り、それをロザリオに見立てたものや、エッケ・ホモやピエタの踏絵などがありました。ロザリオの知恵には、感心しきりです。信仰心の薄い私としては、頭が下がります。
『聖母像(親指のマリア)』はイタリア人宣教師シドッチが描いたもの。マリアがまとう青色のマントは、その色があせることなく今も美しい。マリアの内部から光が溢れ出しています。これを観られただけでも来た甲斐がありました。

浮世絵の部屋では菱川師宣の『見返り美人図』が9/24まで展示されています。浮世絵は度々展示替えされているので、観ていて飽きません。絵や工芸も季節ごとに替わっていて、今は秋の七草が描かれているものが多かったです。
博物館で季節を感じるなんて。外は残暑の陽射しが厳しくて、死にそうでしたから…。
法隆寺宝物館は照明がかなり暗くて、静謐な雰囲気が大好き。たまに閉館間際に行くと、一人きりだったりして。伎楽面は保存のために観られませんでした。残念。
東洋館のインド各地の細密画が良かったです。初めて観ましたよ。クリシュナが描かれている作品が多かったです。シヴァとパールヴァティーとの結婚式のもあったし。詳しくは東京国立博物館のサイトに載っています。
9/17(祝)敬老の日は常設展が無料観覧なんですね。だから今日は空いていたのか…。
学生が卒業制作として自画像を描いたものを収集し、120周年記念事業の一つとして、今回陳列館で展示されることになったそうです。明治31年から始まり一時期途絶えたものの、現在も進行中だとか。
明治期は学ランを来て、真面目に描いているものが多かったです。
その年代によって、絵にも流行があるのかなと思ったり。
藤田嗣治さんはすぐに分かりました。
階段を上がると、昭和から平成の自画像が展示されています。
キャンパスを真っ黒に塗ったものや、静物画の中に自分の頭部石膏像を置いている人もいたり。
自画像という枠にとらわれることなく、自分を自由に表現した作品が増えてきます。
山口晃さんのがなくてがっかり。村上隆さんは、右斜めを向いた自画像で普段着の自分を描かれていました。松井冬子さんは、怖いという印象。
時代を問うことなく、嫌々描いている人、ノリノリで描いている人、は見ていてすぐに分かります。
その後はてくてく歩いて東京国立博物館へと向かいます。
特別展は終了していたのですが、常設展の特集陳列「キリシタン-信仰とその証-」を観たかったのです。ロザリオを禁止されたため、麻の縄に結び目をいくつも作り、それをロザリオに見立てたものや、エッケ・ホモやピエタの踏絵などがありました。ロザリオの知恵には、感心しきりです。信仰心の薄い私としては、頭が下がります。
『聖母像(親指のマリア)』はイタリア人宣教師シドッチが描いたもの。マリアがまとう青色のマントは、その色があせることなく今も美しい。マリアの内部から光が溢れ出しています。これを観られただけでも来た甲斐がありました。
浮世絵の部屋では菱川師宣の『見返り美人図』が9/24まで展示されています。浮世絵は度々展示替えされているので、観ていて飽きません。絵や工芸も季節ごとに替わっていて、今は秋の七草が描かれているものが多かったです。
博物館で季節を感じるなんて。外は残暑の陽射しが厳しくて、死にそうでしたから…。
法隆寺宝物館は照明がかなり暗くて、静謐な雰囲気が大好き。たまに閉館間際に行くと、一人きりだったりして。伎楽面は保存のために観られませんでした。残念。
東洋館のインド各地の細密画が良かったです。初めて観ましたよ。クリシュナが描かれている作品が多かったです。シヴァとパールヴァティーとの結婚式のもあったし。詳しくは東京国立博物館のサイトに載っています。
9/17(祝)敬老の日は常設展が無料観覧なんですね。だから今日は空いていたのか…。
14 .
September
練馬区立美術館にて9/17まで開催中の「山口晃展 今度は武者絵だ!!」に行って参りました。
西武池袋線の中村橋駅からすぐ近くにある美術館。
展示室は四室ありまして、二階から鑑賞して行きます。
二階へ上がる階段の壁には、トップランナーの番組で描かれたマキさんの絵が。
目がらんらんと赤く光り、殺気を放っています。夜中に絵を抜出して、館内を歩き回っていたら怖いなあと想像してしまいました。
やはり第一室の連作「無残の介」がかっこよいのです。刀鍛冶によって、名刀が生み出されるところから始まり、刀の持つ狂気に取り付かれてしまう一人の男。その男の果ては…。
その刀は歴史に埋もれていましたが、ひょんなことからある男の手に渡ります。
山車から登場する機巧のかっちょええこと!!司令部のボスも感動しているぐらいです。
山口さんの絵は、ちょっとしたところに書かれている擬音や言葉が面白いです。
機巧とマキの戦いは如何に?!
馬バイクの作り方、いやあれしかないのですが絵として目の当たりにすると、結構残酷ですよね…。
でも格好いいから好きです。無機物と有機物の融合って、私にとっては子供の時に見た「AKIRA」の鉄雄が強烈だったので。
馬バイクの九相図は、物悲しいです。エンジンまで盗まれて、犬に食べられて。人間の九相図も、腐敗していく様を描いていてカラスに突付かれたりと、白骨になって行く様が描かれています。
なんだろう、馬バイクの場合は矢張りものとして扱われているのが、余計に心苦しいのかな。
頼光と四天王の鬼退治図、シンプルで素敵です。頼光が鬼を踏んづけています。
地獄巡り図も楽しいです。三途の川を渡るときに、皮を脱ぎ捨てて骸骨になる。
その後の世界も、俗世と変わらず。最後の解説四コマが解説になってないのが、また笑えます。
第二室では、私が山口さんにはまる切っ掛けとなった五武人の図や十字軍図、お馬鹿合戦図、頼朝の複製図などが。あの間違い探し、分からなかったのが悔しいです…。武者絵いいな~。
第三室では日露戦争時の絵葉書風の小作品が展示されています。
マグネットなどに商品化されているイラストもありました。
ここでも馬バイクが登場です。
第四室では、成田空港の壁画の下絵や、ブルータスに掲載された若冲双六図、ホラードラコニアシリーズの挿絵、公共広告機構の江戸しぐさのCM下絵など、今までのお仕事クロニクルまであって見ごたえがありました。
一時間半ぐらいかかったかな。これで入館料五百円って、練馬区立美術館さんありがとう!!
足しげく通えないのが残念ですが。
ああもう図録が楽しみですよ。十月中旬に発送だそうです。勿論予約して来ました。
西武池袋線の中村橋駅からすぐ近くにある美術館。
展示室は四室ありまして、二階から鑑賞して行きます。
二階へ上がる階段の壁には、トップランナーの番組で描かれたマキさんの絵が。
目がらんらんと赤く光り、殺気を放っています。夜中に絵を抜出して、館内を歩き回っていたら怖いなあと想像してしまいました。
やはり第一室の連作「無残の介」がかっこよいのです。刀鍛冶によって、名刀が生み出されるところから始まり、刀の持つ狂気に取り付かれてしまう一人の男。その男の果ては…。
その刀は歴史に埋もれていましたが、ひょんなことからある男の手に渡ります。
山車から登場する機巧のかっちょええこと!!司令部のボスも感動しているぐらいです。
山口さんの絵は、ちょっとしたところに書かれている擬音や言葉が面白いです。
機巧とマキの戦いは如何に?!
馬バイクの作り方、いやあれしかないのですが絵として目の当たりにすると、結構残酷ですよね…。
でも格好いいから好きです。無機物と有機物の融合って、私にとっては子供の時に見た「AKIRA」の鉄雄が強烈だったので。
馬バイクの九相図は、物悲しいです。エンジンまで盗まれて、犬に食べられて。人間の九相図も、腐敗していく様を描いていてカラスに突付かれたりと、白骨になって行く様が描かれています。
なんだろう、馬バイクの場合は矢張りものとして扱われているのが、余計に心苦しいのかな。
頼光と四天王の鬼退治図、シンプルで素敵です。頼光が鬼を踏んづけています。
地獄巡り図も楽しいです。三途の川を渡るときに、皮を脱ぎ捨てて骸骨になる。
その後の世界も、俗世と変わらず。最後の解説四コマが解説になってないのが、また笑えます。
第二室では、私が山口さんにはまる切っ掛けとなった五武人の図や十字軍図、お馬鹿合戦図、頼朝の複製図などが。あの間違い探し、分からなかったのが悔しいです…。武者絵いいな~。
第三室では日露戦争時の絵葉書風の小作品が展示されています。
マグネットなどに商品化されているイラストもありました。
ここでも馬バイクが登場です。
第四室では、成田空港の壁画の下絵や、ブルータスに掲載された若冲双六図、ホラードラコニアシリーズの挿絵、公共広告機構の江戸しぐさのCM下絵など、今までのお仕事クロニクルまであって見ごたえがありました。
一時間半ぐらいかかったかな。これで入館料五百円って、練馬区立美術館さんありがとう!!
足しげく通えないのが残念ですが。
ああもう図録が楽しみですよ。十月中旬に発送だそうです。勿論予約して来ました。
ブログ内検索
該当記事が見つからない場合、ブログ内検索をご利用ください。
カテゴリー
リンク
最新記事
(02/13)
(11/04)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
プロフィール
HN:
カンティーナ01
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
当ブログfadaises分館は個人が作成しているものです。関係各社様とは一切関係ありませんので、ご注意ください。製作・著作者の権利を侵害する意図は全くありませんが、なんらかの指摘及び警告を受けた場合には、速やかに文章を削除いたします。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
ブログの内容に関係ないトラックバックやコメントは、削除させていただく場合があります。
最新CM
カウンター
アクセス解析
フリーエリア
Powered by SHINOBI.JP
